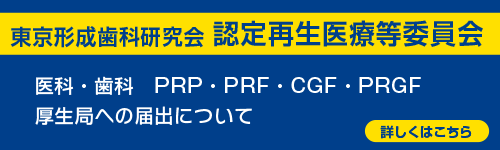2025年度 DH(衛生士)セミナー
2025/09/09
2025年度第1回 日本口腔インプラント学会 認定 DHセミナー
当東京形成歯科研究会会員スタッフの衛生士が統一的な考え、ベクトルを持つことが肝心であるとの思いから、定期的にDHセミナーを開催することとなりました。
今年度、第1回目のDHセミナーを下記の通り、企画致しました。是非、ご参加をご検討下さい。
東京形成歯科研究会DH委員会 委員長 増木英郎

開催日時
2025年10月19日(日) 10:00〜16:00
開催場所(会場)
御茶ノ水トライエッジカンファレンス
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-2-5 御茶ノ水NKビル(トライエッジ御茶ノ水)11階
Tel:03-5289-0177 Fax:
アクセス https://try-edge.infield95.com/access/
参加対象者
歯科衛生士、歯科医師、医療関係者
参加形式
対面
プログラム
講義
〇 医療の質に歯科・医科の区別は必要ですか?「施設評価ツールを使って医療の質について考えてみませんか?」
〇 言語聴覚士(ST)に求められる口腔ケア
~急性期のリハビリテーションと歯科専門職とのかかわりを中心に~
衛生士会員発表
〇2名
タイムスケジュール
09:45 |
受付開始 |
10:00 |
開会 挨拶 増木英郎 |
10:02 |
[講義] 講師・下前 恵 |
12:00 |
昼食(休憩) |
13:00 |
[講義] 講師・杉山明宏 |
15:00 |
休憩 |
15:10 |
[衛生士会員発表]① 発表15分+質疑応答5分 |
15:35 |
[衛生士会員発表]② 発表15分+質疑応答5分 |
15:55 |
閉会挨拶 増木英郎 |
16:00 |
終了 |
参加申込方法
EmailおよびFAX 申込
別紙「参加申込書」に必要事項をご記入の上、下記までご送信ください。
E‐mail:info@tpdimplant.com または FAX:03-3919-5114
※必要事項が認識できれば、「参加申込書」を利用しなくて結構です。Email本文にその旨を記載して下さい。
参加申込締切日
2025年10月3日(金)正午12:00
参加費
1)歯科衛生士 正会員A:5,000円 ※当会会員歯科医師が常勤で在席する医院の歯科衛生士
2)歯科衛生士 正会員B:5,000円 ※当会非会員歯科医師の医院の衛生士
3)歯科衛生士 非会員 :25,000円 ※当会会員の推薦必須
4)歯科医師 会員:無料
*昼食代を含みます。
振込先
銀行名:みずほ銀行
支店名:王子支店(店番号 557)
口座種類:普通預金
口座番号:1517592
口座名義:シヤ)トウキヨウケイセイシカケンキユウカイ
一般社団法人東京形成歯科研究会 代表理事 奥寺元
※「振込手数料」は参加者様にてご負担をお願い致します。
※お振込の際に発行される「振込明細」を領収証と致します。
振込期日
2025年10月15日(水)
お問い合わせ先
一般社団法人東京形成歯科研究会 事務局
〒114-0002 東京都北区王子2-26-2 ウェルネスオクデラビルズ3F オクデラメディカル内
TEL:03-3919-5111 / FAX:03-3919-5114 / E-mail:info@tpdimplant.com
講師ご紹介
テーマ
医療の質に歯科・医科の区別は必要ですか?
「施設評価ツールを使って医療の質について考えてみませんか?」
講師
広島感染防止及び滅菌業務研究会 会長 下前 恵

抄録
私は広島大学病院を定年退職して、現在は医療業界の会社で滅菌管理業務の教育顧問をしています。又、日本医療機器学会の滅菌管理業務検討委員として医療機器の質保証や正しい取り扱い等について検討提案しております。そして、「広島感染防止及び滅菌業務研究会」を開催し医療従事者への講演会も定期的に行っております。
人生のほとんどをこの業界、特に感染防止の分野に費やしてきたことになりますが、今迄何かをしようと計画を立ててもうまくいく事ばかりではありませんでした。むしろうまくいかない事の方が多かったように思います。
これでもかと悩んできたことが私の宝物になり、人間関係をうまく構築していく方法や、協力し合う事の大切さ等など、本当に様々なことを経験させて頂きました。そんな体験から医療の質について私が学んだ事などを中心にお話しできればいいかなと考えております
私は職業柄、医療を提供する側である一方、多くの医療を受ける側でもありましたので、そこからみると自分の体にうける医療行為は、内科でも外科でも歯科でもすべて同じなんです。誰でも最高の医療を受けたいと思っていると思います。そんな中でも歯科と医科には考え方の微妙な違いがあるのを感じていました。
広島大学では2013年から滅菌器材管理室で歯科・医科の全ての使用後器材の再処理業務を行っています。それまでは歯科と医科はそれぞれ別々の診療棟で処理していました。汚染器材の中央化処理になり、歯科器材を受け入れる側の中央材料室では、その処理を一本化するためには様々な問題がありました。そこを乗り越えて現在に至っているのは、当時から積極的に導入した相互間ミーティングです。社会は人と人との繋がりで成り立っています。話し合いで解決できないことは無いと思っています。安全な医療を提供するという目的を共有し、お互いに何をどうすればいいか、困っていることは何かを日常的に話し合い解決していきました。
医療は治療する場所は違っても、感染防止に対する考え方や対応は一緒のはずですし、一緒でなければならないと考えています。例えば、再使用器材の処理についてはしっかり洗浄した後に消毒や滅菌の処理が行われる必要があります。しかし洗浄ができない仕様の器械が普通に販売されている為に、不十分な洗浄のまま消毒や滅菌の処理を行っている現状があります。そもそも洗浄できないのに滅菌だけで器材を使いまわすことのリスクはメーカー側も使用者側もしっかり認識する必要があります。明治に作られた感染症法は大きく変革しており、現代の時代にあった感染防止対策を皆様と一緒に考えていきたいと思っております
テーマ
言語聴覚士(ST)に求められる口腔ケア
~急性期のリハビリテーションと歯科専門職とのかかわりを中心に~
講師
杉山 明宏1),2)
1)公益社団法人有隣厚生会 リハビリテーション部門
2)公益社団法人有隣厚生会 富士病院 リハビリテーション室

抄録
言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist, 以下ST)は,その専門性から他のリハビリテーション関連職種と区別されており,養成課程のカリキュラムにおいては臨床医学・基礎医学に加え,臨床歯科医学の修得が必須と規定されている.これはSTが,歯科専門職と同様に言語機能,発話・コミュニケーション能力ならびに摂食嚥下機能など,患者の「口腔」に関する諸機能の維持および支援を担う専門職であるためである.STの国家資格創設から25年の間に,少子高齢化の進行,医療技術の高度化や情報技術(IT)の発展など,社会環境には著しい変化が認められた.しかしながら,ST養成課程の基準を定めた「言語聴覚士学校養成所指定規則」は,1998年の制定以降,改正が一度も行われてこなかった.2023年9月に発表された「言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会報告書」に基づき,教育内容および臨床実習指導の要件などを追加した新カリキュラムが2025年4月から施行された.その中で臨床歯科医学の領域に「口腔ケア」が初めて明記された.今まさに,STの専門性を活かした口腔ケアが,社会から強く求められている.演者らは,その社会的責任を果たすべく「言語聴覚士が行う口腔ケア―食べる・話す・生きるを支えるために」(2025年6月発刊)を上梓した。
口腔ケアの効果は,口腔および咽頭の細菌数を減少させるばかりでなく,嚥下反射や咳反射の改善に寄与し,誤嚥性肺炎の罹患率を低下させる.近年,その効果は口腔機能の改善およびQOLの向上など多岐にわたることが示唆され,歯科専門職以外の看護職やリハビリテーション専門職においても急性期からの積極的な口腔ケアの実施が推奨されている.一方で,認知機能の低下またはADLの低下によってセルフケアができない高齢者も多数存在し,その対応・介助法に関心が集まっている.
演者は地域の基幹病院で,急性期医療に従事する言語聴覚士である.主に高齢患者の嚥下機能および発話機能の維持向上を目的に積極的な口腔ケアを提供してきた.しかし,令和6年度の診療報酬改定において急性期の在院日数が更に削減される中で,専門職が行う口腔ケアにも更なる検討が必要と考えた.本発表ではリハビリテーション領域で求める結果を出すために,専門職が行う口腔ケアならびに歯科専門職とのかかわりについて報告したい.
【所属、役職】
公益社団法人有隣厚生会 リハビリテーション部門 統括副部長 兼
公益社団法人有隣厚生会 富士病院 リハビリテーション室 技師長
【資格】
言語聴覚士(ST)、修士(健康科学)
認定言語聴覚士(摂食嚥下障害領域)、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士など
【主な専門領域】
高齢者の摂食嚥下リハビリテーション、高齢者に対する口腔ケア(特に触覚過敏や心理的拒否などで介入困難な症例)に興味を持ち,論文執筆および学会発表を行っている。
【主な学会活動】
日本口腔ケア学会評議員、日本口腔ケア学会言語聴覚士部会副部長
【学歴】
愛知学院大学大学院心身科学研究科健康科学専攻博士前期課程修了
【職歴】
知的障害児通園施設児童指導員、脳神経外科専門病院リハビリテーション科を経て、2009年より公益社団法人有隣厚生会富士病院リハビリテーション室に勤務する。主に認知症高齢者および難病患者の嚥下障害、口腔ケアについて臨床、研究に従事した。その他、訪問リハビリテーション(2市2町)、地域包括支援事業(健康増進事業)および専門学校非常勤講師などを経験した。2012年より同室主任、2016年より同室係長、2023年より現職を務めている。