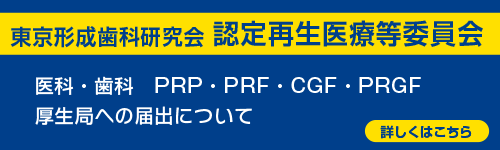【認定講習会および研修会】第12回 2020年3月26日開催
2023/11/09
2019年度 第12回 一般社団法人東京形成歯科研究会 主催 公益社団法人日本口腔インプラント学会 認定「講習会」「修了式/懇親会」開催のご案内
新型コロナウィルス感染予防のため、本講習会の開催を中止する場合がございます。その際は改めてご案内させて頂きますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
↓
“開催中止”
政府や厚生労働省の見解を鑑み、感染拡大を防止するために “開催中止”させていただくこととなりました。
当会会員の先生方、JSOI認定講習会・受講生の先生方、関係各位の先生方におかれましては、このたびの処置につきまして、ご理解くださるようお願い申し上げます。
講演
| 「インプラント周囲炎とインプラント治療におけるティッシュマネジメント」 | |
 |
神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座インプラント・歯周病分野 教授 児玉 利朗 |
| 「インプラントを長く維持させるには」 | |
 |
一般社団法人東京形成歯科研究会理事長・施設長/王子歯科美容外科クリニック 奥寺 元 |
開催概要
※開催概要は予告無く変更となる場合がございます。予めご了承願います。
- 日時
- 2020 年 3 月 29日(日)
- タイムスケジュール
-
- 10:00 ~ 講演「奥寺 元」
- 12:30 ~ 休憩/昼食
- 13:00 ~ 講演「児玉 利朗」
- 16:30 ~ 修了式/懇親会
- 場 所/会 場
- オクデラメディカルインスティテュート セミナー室(5F)
※当日は、「4F・王子フィットネス&ジム」までお越しください。5F セミナー室へは 4F を経由して頂きます。
住所:〒114-0002 東京都北区王子 2-26-2 ウェルネスオクデラビルズ
TEL:03-3919-5111 / FAX:03-3919-5114 ※当日の連絡先 TEL:03-3912-9275 - 受講料
- ○(一社)東京形成歯科研究会主催 JSOI 認定「 講習会 」受講生:無料
※2019 年度(一社)東京形成歯科研究会主催 JSOI 認定講習会 受講料に含まれる。
○(一社)東京形成歯科研究会会員:無料
※2019 年度(一社)東京形成歯科研究会「年会費」に含まれます。
○ 再生医療等提供機関 管理者:要相談(下記「お問合せ先」まで)
○ 一般参加者(受講希望者):25,000 円 - 振込先
- 銀行名:みずほ銀行
支店名:王子支店(店番号 557)
口座種類:普通預金
口座番号:1517592
口座名義:シヤ)トウキヨウケイセイシカケンキユウカイ 一般社団法人東京形成歯科研究会 代表理事 奥寺元
※「振込手数料」は参加者様にてご負担をお願い致します。※お振込の際に発行される「振込明細」を領収書と致します。 - 振込期日
- 2020年 3月 18日(水)
- 参加申込方法
- 別紙「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてお送り下さい。
FAX:03-3919-5114
E‐mail:okudera@carrot.ocn.ne.jp
- 参加申込締切日
- 2020 年 3月 17日(火)12:00 正午
- [お問合せ]
- 東京形成歯科研究会 事務局 担当:押田浩文
〒114‐0002
東京都北区王子2‐26‐2 ウェルネスオクデラビルズ3F オクデラメディカル内
TEL:03‐3919‐5111
FAX:03‐3919‐5114
E‐mail:okudera@carrot.ocn.ne.jp
講演内容
○午前の部
「インプラントを長く維持させるには」
一般社団法人東京形成歯科研究会理事長・施設長/王子歯科美容外科クリニック 奥寺 元
「各種リスクファクター」「インプラント臨床におけるトラブルシューティング」
インプラント臨床における研究が進み各種ガイドラインが教育に定義されつつある。
然し机上の理論が先行して、基礎的理論ばかりで現実味がなく、ともすれば見逃されそれが過失的に考えられて責任を押し付けられる。
永い臨床の中からまた生身を扱う事例から多くの体験に基づいて、現実味のある分析と自ら体験したトラブルシューティングにより有効的な臨床を提言してみたい。
内容は、死亡事故でインプラント臨床が境地に追い込まれた事例に対してその環境に触れる機会があり、その問題点を検証してみたい。
また、何人か訴訟問題にかかわり、学術研究的な立場で弁護をした経緯を説明してみたい。
インプラント臨床医まだ完全なものではなく、多種多様の問題が内包しており良いものだと言う事が先行し過ぎで…保障とかトラブルが無いと言う事が蔓延して自ら命取りになることも有りえる事に警鐘を鳴らしたい。
すなわち未知なる医療を扱いまた形ある物は必ず変化することをしっかり認識して行かなければならない。その様なムンテラ・ラポールもふくめて話していきたい。
奥寺 元
【略 歴】
| 所属学会・認定医 (公社)日本口腔インプラント学会研修施設 一般社団法人東京形成歯科研究会 施設長 理事長 |
|
| 日本口腔衛生学会元理事、指導医 (公社)日本口腔インプラント学会理事 元国際インプラント学会 ICOI 会長 元東京医科歯科大学臨床助教授 ICOI フェロー、ディプロメイト、専門医 国際血液生体材料臨床応用会議理事長 顎顔面口腔インプラント学会指導医 日本有病者歯科医療学会指導医 元 神奈川歯科大学学会選出評議員 |
元顎咬合学会指導医 アメリカレーザー学会指導医 神奈川歯科大学客員教授 台湾 ・ 台北医学大学客員教授 東京医科歯科大学講師 国際口腔美容アカデミー代表 国際顎顔面口腔美容外科学会認定医 日本歯学医学会元予備評議員 第 101 回日本美容外科学会副会長 |
○午後の部
「インプラント周囲炎とインプラント治療におけるティッシュマネジメント」
神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座インプラント・歯周病分野 教授 児玉 利朗
インプラント周囲炎はインプラント治療後の合併症で最も大きな割合を占めていることが報告されている。インプラント周囲炎の特徴は、周囲組織の発赤・腫脹・出血・排膿・歯槽骨吸収である。本態は細菌感染による炎症性病変であり、さらにオーバーロード等の要因も加わり進行するものと考えられる。しかしながら、インプラント周囲炎が発生した場合、それに対応するマニュアル化された対処法として累積的防御療法(CIST)が提唱さているが、現状としては十分な治療法が確立されているわけではない。もちろん炎症性病変であることから細菌感染に対する殺菌もしくは抗菌療法とともにオーバーロードの管理が実施され、その後の再評価により外科的療法の適否を判断することが重要と考えられる。また、外科的療法の選択には、術前の抗菌、角化粘膜の存在、インプラント表面のデブライドメント法、骨欠損形態などの要因を把握した上で、ティッシュマネジメントの概念に基づいて実施されなければ、外科治療の効果は確保されない。
本講演では、インプラント周囲疾患に対する対応と予防の考え方について、ティッシュマネジメントの観点から症例を交えながら検討ならびに考察する予定である。
参考文献 和泉雄一、児玉利朗、松井孝道編著:新インプラント周囲炎へのアプローチ、永末書店、東京、2010 年
児玉利朗
【略歴】
- 1983年
- 神奈川歯科大学歯学部卒業
- 1984年
- 神奈川歯科大学歯周病学講座助手
- 1997年
- 神奈川歯科大学歯周病学講座退職 鹿児島市にて児玉歯科クリニックを開業
- 2006年
- 鹿児島大学歯学部非常勤講(2009 年 3 月まで)(2011 年 4 月~2014 年 3 月まで)
- 2013年
- 神奈川歯科大学客員教授
- 2014年4月
- 神奈川歯科大学大学院歯学研究科 高度先進口腔医学講座 インプラント・歯周病学分野教授就任
現在 歯学博士 歯周病専門医、日本歯周病学会理事・指導医
日本口腔インプラント学会専門医・指導医
九州インプラント研究会会員
ITI フェロー(International Team for Implantology)
神奈川歯科大学附属横浜研修センター・横浜クリニック副院長
神奈川歯科大学大学院歯学研究科 高度先進口腔医学講座 インプラント・歯周病学分野教授