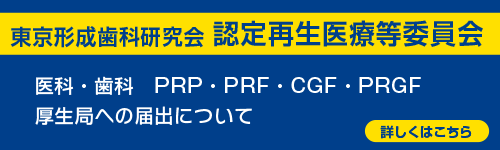【認定講習会および研修会】第7回 2022年10月23日開催
2023/11/08
2022年度 第7回 ※2022年10月23日(日)開催 一般社団法人東京形成歯科研究会 主催 公益社団法人日本口腔インプラント学会 認定「講習会」対面+オンライン(Zoom)のご案内
本講習会は、“対面”参加形式、“オンライン”(Zoom)参加形式のハイブリッド型で開催することとなりました。
※“オンライン(Zoom)”参加形式のみの講義もございます。詳細は下記・開催概要をご確認下さい。
※参加お申し込みが全て“オンライン”の場合は、“オンライン(Zoom)”参加形式のみでの開催に変更させていただきます。
尚、コロナ感染予防対策として、対面式での参加者数を制限し、定数を超えた場合は受講生の参加を優先します。検温実施、消毒等の感染対策を行いますが、自己責任のもとご参加いただくこととします。
新型コロナウィルス感染予防のため、本講習会は ZOOM(インターネット・WEB 会議システム)( https://zoom.us/jp-jp/meetings.html )にてオンライン同時配信いたします。ZOOM での開催は、JSOI へ申請し承認を頂いております。
ご参加なされる先生は、カメラ付きの PC またはタブレット端末(例、iPad)をご用意願います。双方向で会話ができ、PPT等の発表スライドも十分に閲覧可能です。
Zoomへの接続方法が不明な先生は、資料「Zoomアプリのダウンロード~ミーティングを始めるまでの手順」を別途配信させていただきます。当会事務局までEmail送信願います。
〇従来通り、お申し入れがあれば、本講習会開催の数日前に「Zoom“接続テスト”」を実施します。
〇その他、ご不明な点につきましては、どうぞお気軽に当会事務局までご連絡下さい。
講演
| 「補綴専門医が考えるインプラント治療/JSOIケープレ・専修医・専門医試験対策及び認定医更新の注意点」
※講演形式:“ オンライン ” ※「Zoom」配信 〇撮影・録画 禁止 |
|
 |
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座,顎顔面インプラントセンター 教授 大久保 力廣 ※参加形式:“オンライン(Zoom)” |
| 「骨造成の前の注意事項」
※講演形式:“ オンライン ” ※「Zoom」配信 〇撮影・録画 禁止 |
|
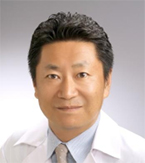 |
医療法人社団 育秀会 早稲田駅前デンタルクリニック/(一社)東京形成歯科研究会 理事 川端 秀男 ※参加形式:“対面”+“ オンライン ” |
| 「歯科治療を成功に導く 欠損歯列の診査・診断と治療計画」
※講演形式:“対面”+“ オンライン ” ※「Zoom」配信 〇撮影・録画 禁止 |
|
 |
医療法人社団 瑞芳会 中村歯科医院/(一社)東京形成歯科研究会 理事 中村 雅之 ※参加形式:“対面” |
開催概要
※開催概要は予告無く変更となる場合がございます。予めご了承願います。
- 日時
- 2022年 10月 23日(日)
- タイムスケジュール ※予告なく変更となる場合がございます。予めご了承願います。
-
- 9:30 ~
- 挨拶 「月岡 庸之(東京形成歯科研究会会長)」 ※“オンライン”参加
講義 テーマ: 補綴専門医が考えるインプラント治療/
JSOIケープレ・専修医・専門医試験対策及び認定医更新の注意点
講演形式:“ オンライン ” ※「Zoom」配信
○講師:大久保 力廣※“オンライン”参加
○座長:川端 秀男※“オンライン”参加 - 11:30 ~
- 講義 テーマ: 骨造成の前の注意事項
講演形式:“ オンライン ” ※「Zoom」配信
○講師:川端 秀男※“オンライン”参加
○座長:調整中※“○○○○”参加 - 12:30 ~
- 症例検討会※ランチョン形式、休憩/昼食
講演形式:“ 対面 ”+“ オンライン ” ※「Zoom」配信※調整中
○症例提供者:市場 敬基※“○○○○”参加※調整中
○座長:礒邉 和重※“オンライン参加※調整中 - 13:00 ~
- 講義 テーマ: 歯科治療を成功に導く 欠損歯列の診査・診断と治療計画
講演形式:“ オンライン ” ※「Zoom」配信
○講師:中村 雅之※“対面”参加
○座長:調整中※“○○○○”参加 - 17:00
- 挨拶(閉会) 「月岡 庸之(東京形成歯科研究会会長)」 ※“オンライン”参加/終了(予定)
- 場 所/会 場 及び Zoom(インターネット・WEB会議システム)接続について
-
※対面形式 + オンライン(Zoom)形式 の「ハイブリッド型」開催となります。
○対面参加形式の場合
オクデラメディカルインスティテュート セミナー室
※当日は、「4F・王子フィットネス&ジム」までお越しください。5Fセミナー室へは4Fを経由して頂きます。
住所:〒114-0002東京都北区王子2-26-2 ウェルネスオクデラビルズ
TEL:03-3919-5111 / FAX:03-3919-5114 ※当日の連絡先(事務局) TEL:090-4913-8677
○オンライン(Zoom)形式参加の場合
Zoomミーティングに参加する※TPDS事務局までお問合せ下さい。
Zoom(インターネット・WEB 会議システム)( https://zoom.us/jp-jp/meetings.html )での開催となります。
講習会当日、下記の内容よりご参加下さい。
ミーティング ID: ※TPDS事務局までお問合せ下さい。
パスワード: ※TPDS事務局までお問合せ下さい。
※部外者からの進入を排除するため、対外秘でお願い致します。
1) Zoomアプリ ダウンロードをお済みでない方
添付「Zoomアプリのダウンロード~ミーティングを始めるまでの手順」の内容に沿って進めていただき、上記の「ID」「パスワード」を使用し、ミーティングに参加して下さい。
2) Zoomアプリ ダウンロードがお済みの方
添付「Zoomアプリのダウンロード~ミーティングを始めるまでの手順」内の“サインイン”からスタートし、上記の「ID」「パスワード」を使用し、ミーティングに参加して下さい。
※講習会当日、ミーティングに参加後、接続できないようであれば、当会事務局(Tel 090-4913-8677)までお電話をお願い致します。参加者の先生からのミーティングの参加を、こちら(事務局)で許可することで、ミーティングへの参加の接続が完了となります。
Zoomアプリのダウンロード ~ ミーティングを始めるまで の手順 - 協賛
- 調整中
- 受講料
- ○(一社)東京形成歯科研究会主催 JSOI 認定「 講習会 」受講生:無料
※2022年度(一社)東京形成歯科研究会主催 JSOI 認定講習会 受講料に含まれる。
○(一社)東京形成歯科研究会会員:無料
※2022年度(一社)東京形成歯科研究会「年会費」に含まれます。
○ 再生医療等提供機関 管理者:要相談(下記「お問合せ先」まで)
○ 一般参加者(受講希望者):25,000 円 ※対面参加形式の場合:昼食代(お弁当)含む - 振込先
- 銀行名:みずほ銀行
支店名:王子支店(店番号 557)
口座種類:普通預金
口座番号:1517592
口座名義:シヤ)トウキヨウケイセイシカケンキユウカイ 一般社団法人東京形成歯科研究会 代表理事 奥寺元
※「振込手数料」は参加者様にてご負担をお願い致します。※お振込の際に発行される「振込明細」を領収書と致します。 - 振込期日
- 2022年 10月 20日(木)
- 参加申込方法
- 下記「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてお送り下さい。
※必要事項が認識できれば、「参加申込書」を利用しなくても結構です。
FAX:03-3919-5114
E‐mail:okudera@carrot.ocn.ne.jp
- 参加申込締切日
- 2022年 10月 14日(金)12:00 正午
- [お問合せ]
- 東京形成歯科研究会 事務局 担当:押田浩文
〒114‐0002
東京都北区王子2‐26‐2 ウェルネスオクデラビルズ3F オクデラメディカル内
TEL:03‐3919‐5111
FAX:03‐3919‐5114
E‐mail:okudera@carrot.ocn.ne.jp
講演
“ 講義 ”
「補綴専門医が考えるインプラント治療/JSOIケープレ・専修医・専門医試験対策及び認定医更新の注意点」
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座,顎顔面インプラントセンター 教授
大久保 力廣
インプラント治療を成功に導くためには診査,診断から,前処置,埋入手術,補綴処置に加え,その後のメインテナンスまで全てのステップに慎重な対応が求められます。その中で,外科主導ではなく補綴主導のインプラント埋入が重視されているのは,最終的な治癒像に補綴の役割が大きいことが認知されているからに他なりません。それでは,補綴に軸足を置いた補綴歯科専門医はどのようなことを考えながら,インプラント治療を行っているのでしょうか? そこで本講演では,インプラント治療に対する補綴の位置付けに関する基本的知識と補綴術式を解説するとともに,デジタルやIRPDついてもお話しする予定です。
【略歴】
大久保 力廣(オオクボ チカヒロ)
1986年 鶴見大学歯学部卒業
1990年 鶴見大学大学院修了
1990年 鶴見大学歯学部歯科補綴学第一講座 助手
1996年 Visiting Scientist, Baylor College of Dentistry
1997年 Assistant Professor, Baylor College of Dentistry
2004年 Visiting Scientist, University of Uruguay
2005年 鶴見大学歯学部歯科補綴学第一講座 講師
2009年 鶴見大学歯学部歯科補綴学第一講座 教授
2016年 鶴見大学歯学部附属病院長
2016年 鶴見大学歯学部インプラントセンター長
2018年 鶴見大学歯学部長
日本補綴歯科学会 専門医・指導医
日本口腔インプラント学会 専門医・指導医
日本顎顔面インプラント学会 指導医
“ 講義 ”
「骨造成の前の注意事項」
医療法人社団 育秀会 早稲田駅前デンタルクリニック/(一社)東京形成歯科研究会 理事
川端 秀男
今回 例会のタイトルが骨増成(GBR)でした。
教育講演を担当 させていただきましたが、骨造成の成功要因 解剖学的な問題点等が不足していたとかんじました。受講生の先生方が骨造成を行う上での注意事項についてお話させていただきたいと思います。
【略歴】
川端 秀男(カワバタ ヒデオ)
- 平成元年3月
- 日本大学歯学部 卒業
- 2年4月
- 日本大学大学院 歯学研究科 臨床系口腔外科入学
- 6年3月
- 同卒業 歯学博士
- 4月
- 日本大学歯学部 助手 口腔外科
順天堂大學口腔外科 医員 - 8年4月
- 早稲田駅前デンタルクリニック 開業
日本大学歯学部口腔外科 インプラント科兼任講師 - 17年
- 東京都国保連合会審査委員
- 19年
- 同退職
- 20年
- 東京形成歯科研究会入会
- 25年
- 日本口腔インプラント学会 専門医
東京形成歯科研究会 理事
日本口腔インプラント学会 代議員 専門医
東京都 四谷牛込歯科医師会
東京都歯科医師会 組織力強化常任委員会 委員長
AO active member
“ 講義 ”
「歯科治療を成功に導く 欠損歯列の診査・診断と治療計画」
医療法人社団 瑞芳会 中村歯科医院/(一社)東京形成歯科研究会 理事
中村 雅之
インプラント治療を希望される患者さんはすでに歯がなくなっているか、これから抜歯になる歯が存在するということであり、何らかの欠損が生じているからこそインプラントが必要になるのである。それはカリエス、エンド、ペリオなど感染が原因であるかもしれないし、破折や(咬合性)外傷などオーバーロードや、医原性疾患との共同原因かもしれない。よく考えなければならないことは、どのようにインプラントを埋入するのかではなく、何故その歯がなくなってしまったか、ということである。インプラント治療にしても天然歯の治療にしても欠損に至った原因がどこにあるかということが理解できなければ治療そのものが失敗に至ってしまうことが考えられる。80歳を超えて全部の天然歯が存在する人の歯列を見るとバランスの取れた歯列(Ⅰ級歯列)を持っている場合が多い。平均寿命男性81.47歳、女性87.57歳であり「人生100年時代」は決して大袈裟ではなく長寿を手に入れた代わりに、考えておかなければならない課題も増えてきており治療後に残るリスクを可及的少なくすることを重要視しなければならない。よって我々が、治療介入後に安定した口腔内を維持させていくためには、総合的に口腔内の状態を評価できる診断力が必要である。そこで今回は、欠損歯列の診断と設計の立案について症例を交えて提示したい。
【略歴】
中村 雅之(ナカムラ マサユキ)
医療法人社団 瑞芳会 中村歯科医院 理事長
資格
・日本口腔インプラント学会 専門医, 代議員
・国際口腔インプラント学会(Clinical Oral ImplantologyDGZI Japan)指導医
・BTI社公認PRGF-Endoret 指導医
・ZimVie Japan 公認インストラクター
・FIDI インストラクター
・日本顎咬合学会 かみあわせ認定医
所属学会 Study Group
・日本口腔インプラント学会
・日本臨床歯周病学会
・口腔病理学会
・日本顎咬合学会
・OJ(オッセオインテグレーション・スタディークラブ・オブ・ジャパン)
・SJCD(Society Of Japan Clinical Dentistry)
・JIADS(The Japan Institute for Advanced Dental Studies) CLAB
・K’sメンバー
・FACE 代表